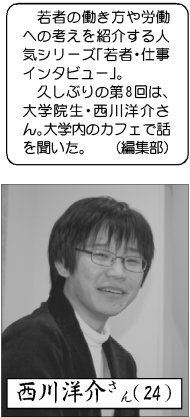[反貧困] 若者インタビュー/バイトを通じた人づきあい、人生の糧に
清掃現場で働く大学生
洋介、今からちょっとおいで」─近所のおばちゃん(中村さん・仮名)に引っ張り出されたのが最初だった。連れて行かれたのはマンションの空き部屋。大手清掃業者の仕事を請け負う会社の現場だ。西川洋介さん(二四)は、大阪市内の大学院生。親許で暮らしながら、アルバイト収入の半分を貯金に、残りを趣味や息抜きにあてている。
中村さんには子どもの頃から面倒をみてもらった。「僕がバイトもせずにぶらぶらしてるのを見るに見かねたんじゃないですかね」。今も裏口から上がってきてキッチンまでやってくるとか。「コミュニティの崩壊」という風潮もどこ吹く風だ。
※ ※
高校生の頃は、ハンバーガーショップでアルバイトをした。話せる仲間と気さくに付き合っていけることが楽しかった。「一つのことをみんなでやっているという感覚。サークルのような。遊びに行く感じ」。
だが、店長が替わって店の雰囲気も変わった。新たに赴任した若い店長は厳しかった。「バイトである以上、店長に従うのが当然だ」。職場からわきあいあいとした雰囲気が消えた。受験準備もあって、しばらくして辞めた。
予備校時代のCDショップでのアルバイトは長く続かなかった。人数が少ない職場で、「社員に嫌われたらやっていけない」という雰囲気。そこで、社員から「あいさつがない」とか「客に声をかけるタイミングが早い」とか、理不尽としか思えない理由で「お前が悪い」と指摘されることが続いた。鬱憤が溜まり、三ヵ月で辞めた。
言葉を交し合う「ぬくもり」学ぶ
今の清掃のアルバイトは引き受けて四〜五年目。「最初はあまり好きなバイトじゃなかったんですよね」と西川さんは振り返るが、仕事を任せてもらえるようになってからは自信もつき、おもしろくなってきた。
「CD屋の時は、「これが悪いあれが悪い」で、人付き合いじゃなかった。中村さんは「マニュアル読んで自分でやれい」じゃなくて、一緒に仕事をやって、自然にやり方が伝わってくる」。中村さんも客との信頼関係を大事にし、押し売りや営業はしなかった。仕事が直接的なコミュニケーション。「仕事しながら自然に仲良くなっていく。そういうところが面白くなってきた」
お客さんとも自然にコミュニケーションがとれるようになった。「ぼくは接客自体は好きじゃない」と言うが、清掃の仕事での人との出会いに楽しさを見いだしている様子だ。「CDを売って終わり」という切断された関係ではなく、言葉を交わし合うぬくもりのあるつながりが面白いという。「冷蔵庫の中とかタンスの中とか、プライベートまで覗く仕事ですからね」
悲しいこともあった。二ヵ月に一回、定期的に通っていた高齢の女性宅。二年ほど前に連れ合いを亡くし、その直後に自身の末期癌がわかった。二ヵ月に一回会いに行くと、投薬の副作用も顕著で、だんだん弱っていくのがわかった。あるとき、仕事のために電話をしたら娘さんが出て「先日亡くなりました」―。「その方の所に行っている時は、仕事というより、一緒の時を過ごしに行くというか、お話しに行くという感じでした」
「最期は自宅で過ごしたい」という人の部屋の掃除もした。「そういう人の最期の場を作ると考えたら、すごく重大なことをしていると思います」

 最新版 1部150円 購読料半年間3,000円 郵便振替口座 00950-4-88555┃購読申込・問合せは
最新版 1部150円 購読料半年間3,000円 郵便振替口座 00950-4-88555┃購読申込・問合せは